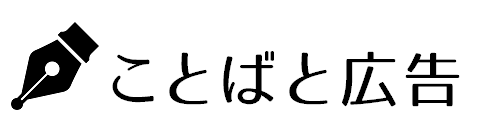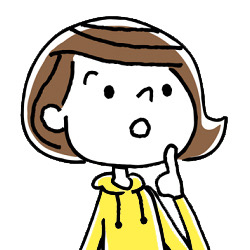先日、BS朝日で『阿久悠 〜昭和が生んだ歌謡界のモンスター〜』を観ました。
若い方には馴染みがないかもしれませんが、ピンク・レディーや沢田研二さんなど、数え上げればキリないほどのヒット曲を生み出した昭和の大作詞家です。
手掛けたヒット曲は5,000曲以上、シングル売り上げ枚数6,000万枚以上ですから、まさに昭和の怪物ですね(ちなみに、わたしも「幼心に聴いたかな」くらいです)。
この方、実はもとコピーライターで代理店で広告やCMを制作していました。そこから、テレビ番組の放送作家となり、作詞の世界へと活躍の場を移されたわけです。
阿久悠さんのすごさは今さら語るもがなですが、「一曲の中に映画のようなストーリー性を持たせた」「1シーン1シーン、劇画のように絵が浮かんでくるようだった」
「それまでの歌謡曲は1カメ(一台のカメラ)だったが、阿久悠さんは複数のカメラで捉えた(ワンフレーズごとに視点が切り替わる)」なんてエピソードは、今聞いてもゾクゾクします。
「それまでの歌詞の世界を壊して、新しいものを作って、世間を驚かせてやろう」という気概が伝わってきますよね。本物のクリエイターです。
そのために、時代が求めていることは何か、どんな言葉が大衆の心をつかむのか、常に言葉を探していたんだとか。これを「時代の飢餓感にボールをぶつける」と表現されていました。
「何を古い話を…」思うかもしれませんが、あれだけのヒット曲を生み出した先人です。現在のポップス、わたしたちが普段使う言葉は間違いなく影響を受けていますよ。
関連 コピーライターの武器である“言葉”は、どこからやってくるのか?
広告制作のクリエイターにいわゆる“作家性”が必要かどうかは、意見が分かれるところでしょう。でも時代を捉えて、時代を作っていくという点では同じです。
温故知新、古きをたずねて新しきを知る。先人に学んで、時代の空気を吸って、次の時代を読んでいきたい。改めて、そう思いました。